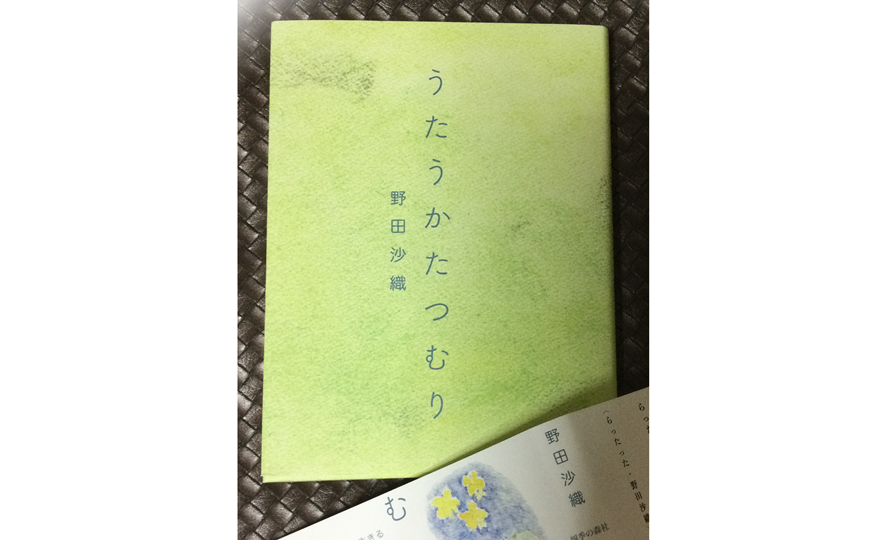憲法発案者をめぐる論争に終止符を、との目的だけなら400頁超の本を手にしなかったろう。GHQの押し付けかどうかは本当に最重要の争点なのか。
著者は序文で、日本国憲法が戦後 日本へ内実化するのがなぜ「未完」に終わったのかについても考察すると述べている。それだよ、大事なのは、と感じたのだ。
なのに、、、表向きの目的はある程度論証できているのかもしれないが、朝鮮戦争と憲法9条成立の議論をいったん切り離してしまったことで、検証作業は憲法成立のところまでで終了している。本書の最後ほんの数頁で触れられている警察予備隊(のちの自衛隊)の成立過程と変遷模様をもっともっと究明してほしいもんだ。警察予備隊こそGHQの押し付けだし、なおかつ、政治家と元軍属の多くがそこに便乗して軍備を維持したがったのではないのか?
本書を読んで、より関心を深めたのは、日米の関係そのものもさることながら、米国からみた東アジア戦後構想の変遷なのだ。それは対中国構想そのものと言ってもいい。(米国はまずルーズベルト大統領の戦後構想でつまずいたわけだが、長い目で見て米国大統領は戦後何度も国際舞台で戦略戦術に失敗しているように思う。)
戦後の米国失敗史と中国躍進史のはざまに日本はゆれつづけている。そうした歴史認識こそ国民が深めるべきだと思う。それが著者の言う、憲法の内実化の一歩にあたらないだろうか。